2. 即席保全の自動プログラム定着とその暴走
私達が注意を向けずに体位維持活動を実行するということは,私達はその体位維持の仕方を脳で自動プログラム化しているということになる。そして,脳で構築したこの自動プログラムに体位維持活動を任せてしまっているということになる。
一定の割合の人は,この即席保全の対処を適宜自動的に動員する自動プログラムを脳で構築していると考えている。つまり,一定の割合の人は,即席保全の対処の仕方を習慣や癖として,何も考慮せずにそれを行ってしまうということである。
実行者が即席保全の自動プログラムを定着させることには,目的とする活動や思考により注意を向けられるというメリットがある。しかし,前章までに述べてきた骨傾斜容認や重心乖離容認,過剰共縮制動の様々なデメリットがあり,こうした様々なデメリットが放置されることで,実行者が被る悪影響も大きい。
実行者が即席保全で体位維持した場合,静止時の姿勢形成において,局所的な筋や靭帯といった組織の負担が大きくなり,呼吸や発声などの機能が制約されることになる。動作時においては,筋緊張が過剰なものとなる。特に,腹筋群と首の筋群の筋緊張が過剰なものとなる。起きている間でいえば,私達が動作,または活動をしていない時間というのは非常に少ないといっていいだろう。このため,実行者が即席保全を定着させていれば,筋緊張が過剰な状態でいる時間は多くなり,負担や機能制約を継続して被ることになる。
即席保全の自動プログラムを定着させることにより,実行者は筋緊張を強くすることになるのだが,これによって実行者は筋緊張を強くしている筋感覚に慣れていくことになる。実行者が筋緊張を強くしている筋感覚に慣れた場合は,実行者は筋緊張を強くしていることに気づきにくくなるだろう。この場合は,筋緊張の程度の差も評価しにくくなるなど,実行者の筋緊張の感覚は鈍くなると考えている。
実行者が,即席保全の対処を脳で自動プログラム化し,実行者が筋緊張を強くすることに慣れて,その筋緊張の感覚を鈍くしてしまった場合は,実行者は「自動プログラムの暴走」ともいえる更なる不利な反応をしてしまいやすくなると考えている。それを次に述べる。
静止時の体位維持に過剰共縮制動を採用する
不利な反応の一つは,実行者が過剰共縮制動を静止状態の体位維持にも採用してしまうことである。この反応はつまり,実行者が本来的には必要のない腹筋群や首の筋群の筋緊張を過剰なものにして静止時に体位を維持してしまう,という反応である。
実行者は静止しているだけで,動作をしているわけではないため,動作による筋の牽引や作用力が体を支える骨に強く働くわけではない。このため,実行者はそもそも制動する必要がないのであるが,この反応は,それにもかかわらず実行者が体を止めようとして過剰共縮制動を行ってしまうという反応である。
実行者が過剰共縮制動を行ってしまう理由はある。それは,実行者がバランス制御に伴う体の動揺を止めようとしているという理由である。私達が立位でいたり,背もたれを用いない座位でいる場合においては,起こしている体は「構造的に不安定なもの」となる。体は,建物や置物のように微動せずに止まるわけではない。体は微小に倒れることになり,そのために私達はそれを元に戻すように体を動かしている。この動きを常に続けている。この動きは,重心動揺として観測されるものである。静止時に過剰共縮制動を行ってしまっている人は,この動揺を止めようとしているのではないか,という考えである。
特に,実行者が「よい姿勢を維持しよう」とする際に,実行者は「よい姿勢の状態で体を止めよう」として,過剰共縮制動を採用しやすいように考えている。一定の割合の人は,そもそも「よい姿勢」を形成する際に,「背すじを伸ばそう」として背筋群を過剰に筋緊張させてしまいやすい。この場合は,同時に腹筋群や首の筋群の筋緊張も強くすることになる。そして,一定の割合の人は,その状態で体を止めようとすることから,過剰共縮制動となって,腹筋群や首の筋群の筋緊張をより強いものとし,それを継続させているように考えている。
私達は体位を維持するにあたって,動揺を止めようとする必要はない。姿勢反射の筋活動で動揺は制御されるものであり,私達は筋緊張を強くしなくとも体位を維持することができる。動揺しながらバランスを維持しているのである。また,実行者が動揺を止めようとして筋緊張を強くしたところで,動揺を完全に止めることはできない。つまり,動揺を止めようとして過剰共縮制動をしていくということは,余計な対処でしかないものである。
しかし,実行者とすれば強い筋緊張の感覚に慣れがあることから,こうした余計な対処をしていることにそれほどの違和感を感じないだろう。むしろ,筋緊張を強くしていることで,「体を止めて支えている」というような適切な処置をしている感覚を得ているかもしれない。
実行者が骨傾斜容認状態の姿勢から「よい姿勢」に修正するにあたっては,実行者は筋を用いることになり,用いられた筋は筋緊張することになる。しかし,修正後の姿勢が立骨重心制御状態であれば,実行者はその状態の維持に姿勢修正時ほど筋を用いる必要はない。姿勢を修正した後は,筋緊張を緩和することができる。実行者は,背筋群を体位維持の主動的な役割として用いることになり,特に腹筋群や首の前側の筋群の筋緊張をある程度緩和させられるようになる。しかし,実行者が筋緊張の感覚に慣れていれば,姿勢修正後の状態維持のために,修正に要した筋緊張を続けてしまうこともあるだろう。
このように,実行者が本来は採用しなくともよかった過剰共縮制動を静止状態の体位維持にも採用している場合は,実行者が筋緊張の強い状態を長時間継続することになり,首の筋の負担が蓄積されて,実行者には筋のこりや張りが起こりやすい。また,腹筋群の筋緊張の継続から,呼吸が制約されることになり,実行者は浅い呼吸を続けてしまうことになる。
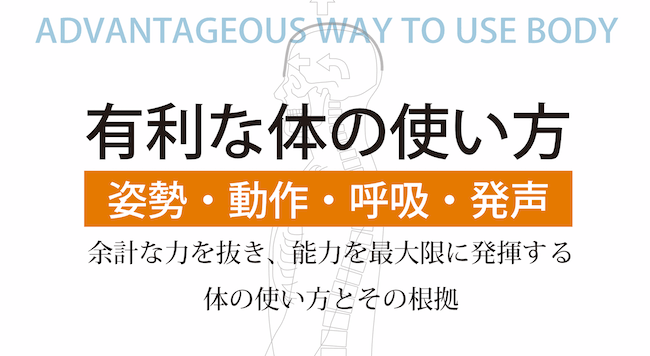

コメント