3. 外界目的注意と自己ユース注意の統合の仕方
外界目的注意と自己ユース注意の適切な統合の仕方
実行者は,必ずしも常に同時的に双方に注意を向けていられるわけではないだろう。どちらか一方に注意が偏る過程があってよい。双方の注意とも,その注意によって実行者が行う作業には思考を要するものを含み,私達は同時に二つのことを思考できないからである。
外界目的注意によって実行者が注意を向けていくことは,外界の状況変化,目的の思考,プランや戦略の思考,意味の理解などで,実行者の思考を要する作業が多い。一方で,自己ユース注意によって実行者が注意を向けていくことは,立骨重心制御で体全体の重心や体を支える骨を位置づけていくことや,過剰共縮制動を抑制して重鎮基底制動を採用していくこと,先導端への意識,呼吸の仕方の確認などであり,感覚を用いた状態確認と思考を要する作業を含む。実行者が自己ユース注意を持つ際に,それが感覚を用いた状態確認の作業に注意を向けている時は,外界目的注意において思考作業することも可能であり,同時に注意を向けられて双方を両立しやすいだろう。しかし,自己ユース注意を持つ際に思考を伴う体の制御に注意が向けられる時は,外界目的注意で思考を用いることができず,外界目的注意については外界状況視認などの感覚による情報収集作業に留まることになる。両立することはできるものの,実行者の注意は自己ユース注意に少し偏る形となるだろう。
例えば,実行者が自身が骨傾斜容認状態でいることに気づいて立骨重心制御状態に是正していく段階や,行為の前に過剰共縮制動ではなく重鎮基底制動のプランを持つ段階では,実行者は選択する必要があり,思考することになる。このため,実行者はその注意の多くを一旦は外界目的注意から自己ユース注意に向けていくことになる。しかし,実行者が是正した後の立骨重心制御状態を維持する段階や,重鎮基底制動の基に目的行為を遂行していく段階では,実行者は固有感覚や触覚や圧覚などの体性感覚で状態を確認しながら体を制御しており,外界の状況変化や目的のことを思考する余地を増やすことができる。この段階では,実行者は自己ユース注意への配分を少なくでき,外界目的注意により多くを向ける形で双方を両立させている。
このように,実行者はどちらかの注意に全て向けている段階と,どちらかに多く偏りつつも両立している段階とがあると考えてよい。実行者が常に双方に同程度の注意を向けなければならないと考えてしまうと,その難しさから混乱しやすくなる。
また,自己ユース注意によって実行者が向ける注意の対象は,頭から支持部位までの部位,重量バランス,呼吸と多岐に渡る。実行者は自己ユース注意で,自身の体の使い方を常に完全な形で制御していこうとすると,その制御する作業と情報の多さから,やはり混乱しやすい。実行者は自身の体の使い方の全てを常に完全な形で制御していくというよりは,ある瞬間は「支持部位と動作の先端を導くこと」を考え,また気づいた際に「頭の制御」のことを考えたり,「呼吸」のことを考えたり,とそれぞれの注意対象に個別に気づいて是正していくようなものであってよい。一定の時間内で全ての,または多くの制御を達成していくと考えた方が現実的で無理がないと考えている。
外界目的注意と自己ユース注意の注意の配分の仕方について具体的に言えることの一つは,タイミングである。実行者は動作を開始する少し前に,自己ユース注意を持つべきである。つまり,自身の体の使い方に気づくことである。即席保全の対処パターンは,動作の直前に自動的に行われやすいからであり,実行者は事前の段階で自己ユース注意を持つようにして,この対処パターンから脱却するのである。実行者は,そこで立骨重心制御を行い,重鎮基底制動のプランを持ち,これらをその後の動作中に実行していく動作イメージを形成する。その上で,外界目的注意の配分を増やして動作していく。このように,実行者は動作する前の段階で自己ユース注意を持ち,その上で動作していくとよい。実行者は,その後も外界目的注意を持ちながら,適宜自己ユース注意への配分を増やして確認していくようにする。
一定の時間内における双方への注意量の配分比でいえば,多くが外界目的注意に配分されることになり,自己ユース注意への配分は相対的に少ないものとなろう。私の個人的な感覚でいえば,慣れていることもあって自己ユース注意は5%くらいの配分であるように思う。これは注意量の配分であるが,時間的な配分ともいえるかもしれない。これは私個人の感覚的な評価であり,一つの目安として考えてもらいたい。
実行者が日頃から実践を重ねて立骨重心制御や重鎮基底制動に熟達していれば,非常に短い時間でそれらを制御することができるようになり,そのための思考や状態確認に要する注意量も少なくすることができる。
実行者が立骨重心制御や重鎮基底制動に熟達した結果,それらが自動的に制御されるように感じる場合もあるだろう。しかし,有利意図の人は,それをもって自己ユース注意を持つ必要がなくなるとは考えない方がよい。実行者が確認せずに放置した結果,元の骨傾斜容認状態や無思慮な過剰共縮制動の採用に陥っている可能性は十分にある。自己ユース注意を外界目的注意と共に持つことが自身の習慣となっていることを目指すとよい。つまり,「時折に自動的に自身に気づく」ような状態を目指すのである。
それまでの注意の向け方が外界目的注意のみだった人が,自己ユース注意を加えて双方を統合させていく場合は,それまでの外界目的注意から注意を逸らすこととなる。このため,実行者は集中しておらず,散漫に感じたりするもしれない。しかし,それは集中を逸らしているわけではない。新たな注意である自己ユース注意とは,行為と関係のない余計なことに向ける注意ではなく,行為の成否や効率に関係する体の使い方への注意である。つまり,自己ユース注意を加えることは,実行者が行為に関係のある全ての情報に注意を向けていくことであり,意味のあるものとなる。変化を与えていく過程では,実行者はこれを「新しい集中の仕方」と考えるべきである。
なお,自身の体の使い方の制御に関する情報量は多い。外界目的注意に加えて自己ユース注意を加えるということは,扱う情報量が一気に増えることになる。しかし,これは実行者がその行為に集中していくにあたっては良い方向に貢献する。扱う情報量が増えたことで,実行者はその他のことを思考する余地が少なくなるからである。実行者がある行為をする際に,その行為とは全く関係のない余計なことを思い浮かべる場合があるが,この余計なことを考える余地が減ることになる。
心理的プレッシャーが実行者にかかる場面においては,実行者は行為の失敗などに対する不安や心配を感じて,その失敗した状態を無自覚にイメージしていたり,その後にどうなるかを考えていたりするかもしれない。実行者は扱う情報量を増やすことで,この不安や心配に向かう思考の余地を減らすことができるのである。不安や心配といったネガティブなことは私達の脳裏によぎりやすく,かつ留まりやすい。しかし,実行者が不安や心配について考えていたところで,現実の状況は悪化こそすれ,好転はしないだろう。
実行者は自己ユース注意を加えることで,こうした場面で自動的に起こりやすいネガティブな思考を希薄なものにできる。実行者は扱う情報量が増えていることをポジティブにとらえて,今現在の自分のやるべきことに注意を向けるようにするとよい。
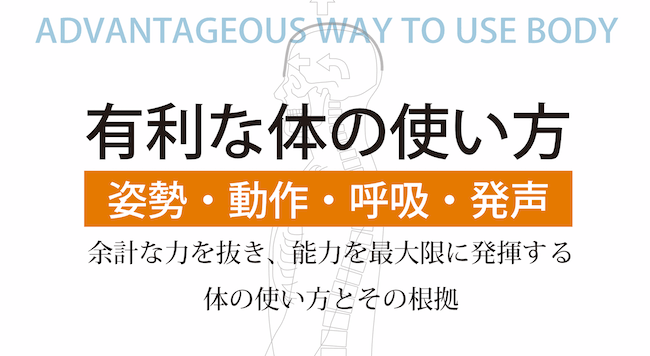

コメント