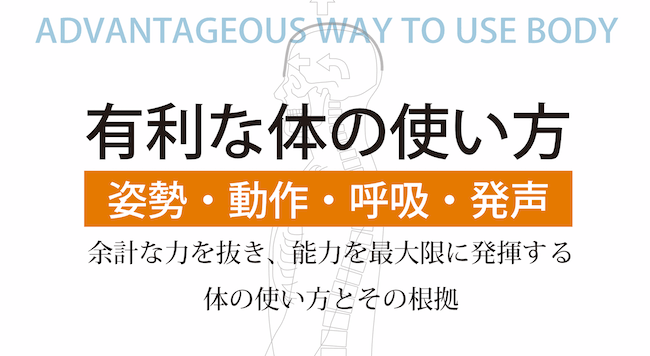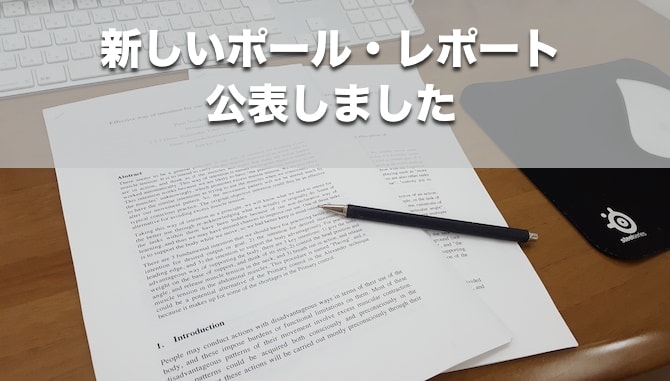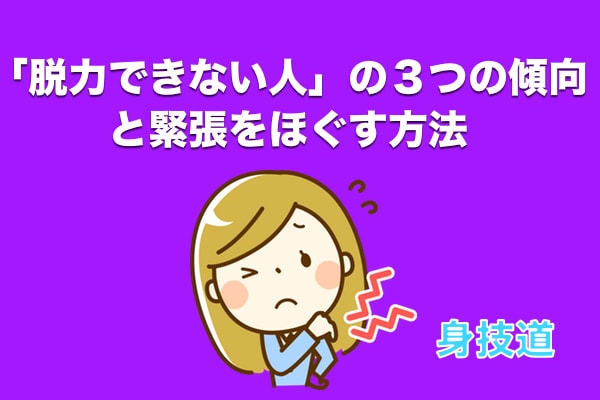miwazado– Author –
-

第2章 動作時の有利な体位維持の仕方(その9)
【3. 実際の体の動作における体位維持の仕方による違い(つづき)】 重鎮基底制動 立骨重心制御の状態が動作時に維持されるためには,支持部位の抑止が前提となることが先のモデルから考察された。支持部位の抑止が適切に行われることで,有利な動作が導... -

新しいポール・レポートを公表しました
【新しいレポートを公表】 海外にはより多くの先生や取り入れている人たちがいて、そうした方々にも私の考え方を伝えたかったので。 3月にニューヨークで音楽家向けのワークショップを行いますが、そこではこの考え方もデモンストレーションしてくるつも... -

第2章 動作時の有利な体位維持の仕方(その8)
【3. 実際の体の動作における体位維持の仕方による違い(つづき)】 発声時の体位維持の仕方による違い(つづき) 次に,実行者が立骨重心制御の態度でいて,その状態で発声していく場合を考え,その特徴を骨傾斜容認状態や重心乖離容認状態の時と対比す... -

「脱力できない人」の3つの傾向と、緊張をほぐす方法
「力が入ってますねー、もっと力を抜いてやってみましょう」 学びごとではよく聞く表現です。 これを言われてすぐにできる人もいますが、できない人もいる。そして、できない人は、様々な場面でこうした表現を人から指摘されたりするかもしれません。 脱力... -

第2章 動作時の有利な体位維持の仕方(その7)
【3. 実際の体の動作における体位維持の仕方による違い(つづき)】 発声時の体位維持の仕方による違い 次に発声の事例で考える。これも立位で行うことを前提に考える。そして,図2—5のように,実行者が最初から骨傾斜容認状態でいて,骨盤スライド後傾... -

第2章 動作時の有利な体位維持の仕方(その6)
【3. 実際の体の動作における体位維持の仕方による違い(つづき)】 上肢動作の体位維持の仕方による違い(つづき) 骨盤スライド後傾の動きが進み過ぎて,体の重心が適切位置から後方に乖離することもある。実行者が重心乖離容認の態度でいれば,これは... -

第2章 動作時の有利な体位維持の仕方(その5)
【3. 実際の体の動作における体位維持の仕方による違い(つづき)】 上肢動作の体位維持の仕方による違い 上肢の動作,つまり腕や手を用いた動作をまずは考える。実行者が立位の状態で,右手に重りを持って肘を曲げて,それを肩の高さまで持ち上げるとい... -

第2章 動作時の有利な体位維持の仕方(2章その4)
【3. 実際の体の動作における体位維持の仕方による違い】 モデルと実際の体との違い 前節では,モデルにおける動作時の体位維持の仕方による違いについて述べた。このモデルは架空の構造であり,実際の体とはかけ離れているものである。しかし,このモデ... -

第2章 動作時の有利な体位維持の仕方 (2章その3)
【2. モデルでみる動作時の有利な体位維持の仕方(つづき)】 重心制御の有利性 また,重心乖離容認は,骨傾斜容認と同様に,動作時においても不利な体位維持の仕方となる。それを,前述したモデルから考察できる。 ここで,床面上で停止していると仮定し... -

第2章 動作時の有利な体位維持の仕方 (2章その2)
【2. モデルでみる動作時の有利な体位維持の仕方】 動作時には,第1章で説明した立骨重心制御による体位維持の仕方が,制動にとっても有利な体位維持の仕方となると考えている。つまり,立骨重心制御状態で行う動作の仕方が,有利な動作の仕方となると考...